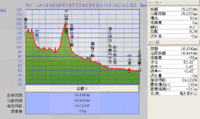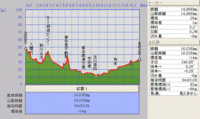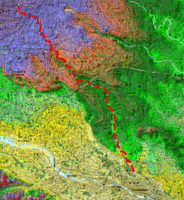ひとつは調布から京王線に沿って、旧甲州街道・甲州街道を杉並・和泉まで歩くルート。これは会社の社員の家が国領にあり、ちょっとした御もてなしを受け、お開きとなり歩いて帰宅した時。
もうひとつは調布から深大寺、東八道路をへて久我山から杉並・和泉へのルート。これは娘の調布マラソンの応援に出向き、帰り道を歩くことにした時。もう半年もむかしのことなので、記憶ほとんど残ってはいない。が、ともあれ調布>甲州街道ルート。
調布>甲州街道ルート
国領
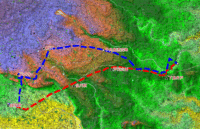 調布駅スタート。旧甲州街道を布田方面に。布田は麻布の材料となる麻生の材料が植えられた土地・田があったのだろう。国領駅に。日本橋から数えて4番目の宿場。駅前に異様な高層マンション。ランドマークにはなるだろうが、少々違和感。で、国領の由来。古代から中世にかけての国衙領、つまりは荘園に対する公領がこの地にあったからだろうか。そういえば近くに、飛田給とか、上給といった地名もある。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)
調布駅スタート。旧甲州街道を布田方面に。布田は麻布の材料となる麻生の材料が植えられた土地・田があったのだろう。国領駅に。日本橋から数えて4番目の宿場。駅前に異様な高層マンション。ランドマークにはなるだろうが、少々違和感。で、国領の由来。古代から中世にかけての国衙領、つまりは荘園に対する公領がこの地にあったからだろうか。そういえば近くに、飛田給とか、上給といった地名もある。(「この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平21業使、第275号)」)国領駅を過ぎると、旧甲州街道は甲州街道に合流。これからしばらくは車の排気ガスをたっぷり吸うことになる。調布警察署前を越えるとすぐに野川と交差。柴崎駅を越え、つつじケ丘交番前を右折。
京王つつじケ丘駅前に入る。駅前に書源という書店。どこにいっても金太郎飴みたいな書店が多いこのご時世、この本屋さんだけは品揃えに何かを感じる。とはいいながら、一時期いろんな店を探し回ったがなかなか見つからなかった『国銅(上・下)』(帚木蓬生著・新潮社刊)がこの店にあったという理由だけなのだが。見つけたときは結構うれしかった。
国分寺崖線
京王線にそって進む。入間川を越えたあたり、前方に壁。いわゆる国分寺崖線であるのだが、そのときは崖線といった言葉も知る由もなく、ひたすら、壁に圧倒される。どこから上ればいいか、壁の割れ目を探す。急な坂。上りきる。と、脇に実篤公園があった。実篤公園については先日の散歩でメモしておいた。
仙川駅を越え、足元に京王線を見ながら進む。結構丘が高い。丘を下り仙川に。川沿いの遊歩道を甲州街道まで戻り、再び旧甲州街道に。
給田地区。給田という以上、このあたり、幕府や荘園領主が御家人・荘官に給料のかわりに「田」をあたえていたのだろう。こうして律令制の基本となる、公地公民制が崩れていくのだろう。
ともあれ、京王線千歳烏山、芦花公園と進む。烏山はカラスの多く巣くう森があったからとか、黒い土からなっていたとか。千歳は歴史的由来なし。いくつかの村が合併するとき、御めでたい名前をつけただけ。芦花公園は明治の文豪徳富蘆花の住居「蘆花恒春園」が近くにあったから。「不如帰」とか「自然と人間」などで知られる。
そういえば、逗子の海岸端、田越川が逗子湾に注ぐ河口に蘆花記念公園があった。その地が「不如帰」を執筆したところだと。また、逗子海水浴場の鎌倉寄りのところに浪子不動がある。不如帰の舞台ともなったところであり、ヒロイン浪子の名前をとったお不動さんがつくられたのだろう。
環八手前で旧甲州街道は甲州街道と合流。環八を過ぎ、八幡山、上北沢、桜上水から下高井戸に。八幡山は八幡神社がある里山というか森、というか林があったから。「桜上水」は、近くの玉川上水の堤に桜並木があったことから。高井戸は、高いところに井戸があったから、とか、高いところにお堂=高いお堂=たかいど、となったとか、これも例によっていろいろ。下高井戸は日本橋から数えて2番目の宿場町。あとは、神田川沿いに遊歩道を歩き和泉の我が家まで歩き本日の予定終了。
甲州街道
で。甲州街道。徳川幕府が制定した5街道のひとつ。日本橋から甲府、ではなく信州・下諏訪までの53里の街道。このメモをまとめるまで、甲州=甲府まで、と思い込んでいた。江戸初期は参勤交代にこの街道を利用するのは、伊那の高遠藩、飯田長姫の飯田藩、諏訪の高島藩の3大名のみ。中仙道に比べて閑散としていたようだ。下高井戸宿あたりなど、昼なお暗きといった様相だったとか。が、将軍家御用のお茶を宇治から江戸まで運ぶ「お茶壺道中」がはじまった頃、5代将軍綱吉の頃からは少々賑わいをみせてくる。ちなみに徳川幕府制定の5街道とは、東海道、中仙道、甲州街 道、日光街道、奥州街道。
調布>深大寺>東八道路
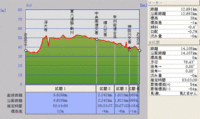 調布から杉並・和泉への散歩道のあとひとつは、甲州街道を離れ深大寺>東八道路>中央高速道交差>環八>和泉へのルート。
調布から杉並・和泉への散歩道のあとひとつは、甲州街道を離れ深大寺>東八道路>中央高速道交差>環八>和泉へのルート。調布から旧甲州街道を布田駅まで歩き、布田駅交差点を左折、甲州街道の下布田交差点を北に三鷹通りに。八雲台交差点を越え、野川と交差。佐須町の交差点を越え、中央高速の下をくぐれば深大寺湿地。
が、しかし、ここに湿地があることは、このメモをまとめることになってはじめてわかった。深大寺散歩をした当時、といっても半年前だが、その頃はただひたすら歩くだけ。地形のうねりも、湧水も、崖も、城址も頓着しなかった。
で、深大寺湿地を見落とし深大寺小学校前に。結構歴史のありそうな学校。実際、前身となる学校は明治6年、というから、「邑ニ不学ノ戸ナク 家ニ不学ノ人ナカラシメン」といった明治5年の学制令発布の翌年に建てられたという。深大寺の末寺、多門院を使ってはじめたとのこと。左に曲がれば深大寺の入口だったようなのだが、道案内がよくわからず坂を直進。青渭神社前に。
青渭神社
縁起;往古、この辺りに大きな青い沼。ために、青沼大明神とも呼ばれる。祭神は青渭神。出雲系・農耕・農作物の神。本殿の建築は、江戸時代初期のもの。ケヤキは、市天然記念物。
深大寺
神社を出て、結構今風の公園脇を深大寺植物公園に向って奥に進む。適当なところで左折し深大寺へと。途中鬱蒼とした森というか林を進む。つまるところは、深大寺の裏手からアプローチとなったわけ。深大寺は天台宗の古刹。天平5年(733)、満功(まんくう)上人によって創建されたと伝えられる、関東では浅草寺についで古い寺。
深大寺周辺は国分寺崖線が通り、「ハケ」から湧く豊富な水が、せせらぎや滝をつくる。釈迦堂には白鳳仏。奥の木立の中に、秘仏をまつる水神深沙大王堂がある。
深沙大王堂といえば、深大寺縁起にこんな話しが;その昔、この地は郷長右近(さとおさうこん)によって治められていた。福満(ふくまん)という青年が現れる。右近の娘と恋に落ちる。右近は二人の仲を許さず、娘を池の島へ隠す。福満は深沙大王にお願いの儀。「大王様のお力で、島に渡らせてほしい。願い叶えば、里の鎮守としておまつりする」と。池から霊亀が現れる。福満は亀の背中に乗り島へ渡り娘を助け出す。右近も二人の仲を認め、結婚を許す。子は満功(まんくう)。父と深沙大王との約束を受け継ぎ、唐へ渡り、教義を究めてこの地に戻り、733年に深大寺をつくったと。福満といい満功といい、いかにも渡来系。古来、調布から狛江にかけて移り住んでいた渡来系氏族と武蔵野の地に住んでいた先住氏族の異文化交流を表しているのかも。
深大寺からは三鷹通りを離れ住宅街というか農家・畑の間を東に向う。中央高速手前、昇華学園交差点あたりで北に。原山交差点、中原3丁目の交差点、杏林大学病院入口を越え、仙川公園を過ぎれば仙川と交差。新川交番前交差点で東八通りに。
東八道路を天神前北浦、新川天神前、三鷹台団地入り口と進む。このあたりで道路が狭くなる。牟礼地区を進む。が、歩道はない。車に気を使いながら国学院久我山を過ぎ、NHK運動場の近くを進む。このあたり、玉川上水散歩で歩いた。ずっと続いた玉川上水の開渠が暗渠と消える地点。さらに進み中央高速にあたる。後は中央高速に沿って、高井戸出口、第六点神社を越え環八から一路和泉まで。
深大寺湿地、そしてそ深大寺城址
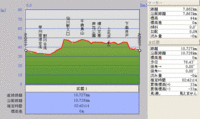 で今回見逃した深大寺湿地、そしてその中にある深大寺城址についてメモしておく。本当にこの時代は敵味方錯綜し、なにがなんだかわからなくなってしまう。はてさて、この深大寺城址をめぐる人物・イベントであるが;
で今回見逃した深大寺湿地、そしてその中にある深大寺城址についてメモしておく。本当にこの時代は敵味方錯綜し、なにがなんだかわからなくなってしまう。はてさて、この深大寺城址をめぐる人物・イベントであるが;1.作った人;扇谷上杉朝定。武州松山の難波田弾正広宗に命じ古い砦跡を急遽改修してつくった
2.目的;後北条氏、北条氏綱の侵攻に備える。後北条氏とは、伊勢新九郎長氏(後の北条早雲)を初代とする小田原北条氏五代。鎌倉時代の執権北条氏と区別して「後北条氏」と呼ぶ。
3.経緯;室町幕府の支配権が衰えると世は戦国時代へ。そんな16世紀前半、関東は管領上杉氏と北条早雲を祖とする新興勢力の後北条氏との覇権を争う場となっていた。北条氏綱が高縄原合戦(現在の高輪台)で勝利し江戸城を奪取。扇谷上杉氏の本拠・河越城攻撃を計画。それに備えるためつくったのが深大寺城。
4.カウンター:北条氏綱は牟礼・烏山に砦、深大寺城に対する付け城を築いて封鎖し、深大寺を力攻めすることなく、河越城へ進む。
5.武藏三ツ木原(西武新宿線・新狭山)で扇谷上杉軍と合戦。北条氏勝利。一気に上杉勢の本拠地である河越城まで一気に侵攻。
6.結果;上杉軍は総崩れ。河越城を捨てて松山城に退却。江戸城攻防から河越城攻防までは一方的に北条氏の勝利。その後の第一次国府台合戦、そして日本三大夜戦のひとつとも呼ばれる河越夜戦において北条氏決定的勝利。関東の覇者として君臨
7.深大寺城の位置づけ;戦略的意味がなくなり。廃城。
8.ついでに;高縄原の激戦(高輪台)。大永4年(1524年)、江戸城を守る扇谷上杉朝興(太田道灌を暗殺した扇谷上杉定正の2代あと)と、関東攻略を図る北条氏綱が高縄原(今の高輪台辺)で激突した。上杉軍、江戸城へ退却。太田道灌の孫、太田資高、資貞兄弟の内応で江戸城は陥落。そして夜になると闇にまぎれて川越へ落ちる朝興を板橋近辺まで追撃。勝った北条軍、一ッ木原(赤坂),勝鬨を。
ともあれ、この深大寺あたり、お寺とかそば以外に地形的にも面白い。日を改めて再度歩くべし。
6.結果;上杉軍は総崩れ。河越城を捨てて松山城に退却。江戸城攻防から河越城攻防までは一方的に北条氏の勝利。その後の第一次国府台合戦、そして日本三大夜戦のひとつとも呼ばれる河越夜戦において北条氏決定的勝利。関東の覇者として君臨
7.深大寺城の位置づけ;戦略的意味がなくなり。廃城。
8.ついでに;高縄原の激戦(高輪台)。大永4年(1524年)、江戸城を守る扇谷上杉朝興(太田道灌を暗殺した扇谷上杉定正の2代あと)と、関東攻略を図る北条氏綱が高縄原(今の高輪台辺)で激突した。上杉軍、江戸城へ退却。太田道灌の孫、太田資高、資貞兄弟の内応で江戸城は陥落。そして夜になると闇にまぎれて川越へ落ちる朝興を板橋近辺まで追撃。勝った北条軍、一ッ木原(赤坂),勝鬨を。
ともあれ、この深大寺あたり、お寺とかそば以外に地形的にも面白い。日を改めて再度歩くべし。