堰堤から山口貯水池や狭山丘陵に集まる芝増上寺の石灯籠の「謎」、トトロの森の自然、そして最後は都下唯一の国宝建造物であるお寺さまで最後を締めることにする。
玉湖神社

 「羽村・山口」軽便鉄道の最後の隧道(6号隧道)をフェンス越しに見遣り、あっけなく終わった廃線歩きから気分を切り替え、狭山湖周辺のハイキングのガイドとして先に進む。
「羽村・山口」軽便鉄道の最後の隧道(6号隧道)をフェンス越しに見遣り、あっけなく終わった廃線歩きから気分を切り替え、狭山湖周辺のハイキングのガイドとして先に進む。西向釈迦堂
 道脇の少し小高いところに西向釈迦堂。丘陵下にある金乗院・山口観音の一堂宇である。釈迦堂の境内には歌碑が建つとのことだが見逃した。ダム管理事務所の所長を務め、一帯を桜の名所とした方の詠んだ句碑とのこと。「浮寝して 湖(うみ)の心を 鴨はしる」と刻まれる、と。
道脇の少し小高いところに西向釈迦堂。丘陵下にある金乗院・山口観音の一堂宇である。釈迦堂の境内には歌碑が建つとのことだが見逃した。ダム管理事務所の所長を務め、一帯を桜の名所とした方の詠んだ句碑とのこと。「浮寝して 湖(うみ)の心を 鴨はしる」と刻まれる、と。山口観音は一度訪れたことがある。新田義貞が鎌倉攻めのときに戦勝祈願をしたとも伝えられる古いお寺さま。ダムができる前からこの地にあったのだろうが、現在はマニ車があったり、中国風東屋、ビルマ風パゴダなどが建ち、いまひとつしっくりしないので今回はパスしダム堰堤に向かう。
山口貯水池堰堤
 桜の植樹をひとりではじめ、一帯を桜の名所とした所長が勤務したであろうダム管理事務所前を通り山口貯水池堰堤に。西は広大な貯水池、東は柳瀬川が開析した谷筋の眺めが美しい。
桜の植樹をひとりではじめ、一帯を桜の名所とした所長が勤務したであろうダム管理事務所前を通り山口貯水池堰堤に。西は広大な貯水池、東は柳瀬川が開析した谷筋の眺めが美しい。狭山丘陵ははるか昔、多摩川が造り上げた扇状地、それは青梅を扇の要に拡がる武蔵野台地も含んだ巨大な扇状地であるが、そこにぽつんと残る丘陵地である。
狭山とは、「小池が、流れる上流の水をため、丘陵が取りまくところ」の意とも言う。この語義の通り、かつては柳瀬川が浸食した狭い谷あいの水を溜め、農業用水や上水へと活用していたこの狭山丘陵の浸食谷を、昭和9年(1934)に堰止めつくりあげたのが狭山湖(山口貯水池)である。
羽村取水堰と小作取水堰より導水され狭山湖(山口貯水池)に貯められた水は、ふたつの取水塔をとおして浄水場と多摩湖に送られることになる。第一取水塔からは村山・境線という送水管で東村山浄水場と境浄水場(武蔵境)に送られ、第二取水塔で取られた原水は多摩湖に供給される。また、多摩湖(村山貯水池)からは第一村山線と第二村山線をとおして東村山浄水場と境浄水場に送られ、バックアップ用として東村山浄水場経由で朝霞浄水場と三園浄水場(板橋区)にも送水されることもある、と言う。
狭山不動尊
堰堤を離れ、次は狭山不動尊に向かう。このお不動さんに訪れたのはこれで三度目である。最初は全国から集めた著名な建造物や幾多の徳川家ゆかりの石灯籠・宝塔が並ぶ、といったそれなりの印象で通り過ぎたのだが、いつだったか辿った清瀬散歩で気になった出合いを深掘りすると、狭山不動にからむおもしろい歴史が登場し、そのエビデンスを確認しに再訪。そして今回は三回目。そのストーリーをパーティの皆さんに「共有」すべくご案内することにした。
経緯はこういうことである;清瀬を散歩しているとき、それほど大きなお寺さまでもないのだが、その境内に誠に立派な一対の宝塔が並び、それは徳川将軍家の正室の墓碑であった。また、境内には15基の立派な石灯籠もある。徳川将軍家の法名や正室、側室の法名が記されている、とのことである。
はてさて、何故に清瀬のこの地に徳川将軍家ゆかりの宝塔(墓碑)や石灯籠があるのだろうと気になったのでチェックすると、なかなか面白い歴史が現れてきた。
ことのはじめは昭和20年(1945)の東京大空襲。徳川将軍家の霊廟(墓所)がある増上寺の大半が灰燼に帰した。廃墟となった霊廟跡は昭和33年(1958)に西武鉄道に売却され、東京プリンスホテルや東京プリンスホテルパークタワーとなる。そして廃墟に散在していた将軍家ゆかりの宝塔や石灯籠は、西武鉄道の手により狭山の不動寺に集められる。
一部は狭山不動寺に再建されるも大半は野ざらし。その敷地も西武球場とするにあたり、宝塔や石灯籠の引き受け手を求めたようである。清瀬のお寺様で見た、宝塔や石灯籠はその時に狭山不動寺から移したものであった。
●桜井門

 堰堤から狭山不動に向かう。丘陵下の正面から入ることなく、堰堤に続く道から直接お不動さんの境内に入る。奈良県十津川の桜井寺の山門を移築した桜井門から境内に入る。灯籠群脇、道の両側に石灯籠が並ぶ。
堰堤から狭山不動に向かう。丘陵下の正面から入ることなく、堰堤に続く道から直接お不動さんの境内に入る。奈良県十津川の桜井寺の山門を移築した桜井門から境内に入る。灯籠群脇、道の両側に石灯籠が並ぶ。●青銅製唐金灯籠群

 中を先に進むと灯籠群に四方を囲まれ、港区麻布より移築された井上馨邸の羅漢堂が佇む。その裏手の囲いの中にはおびただしい数の青銅製唐金灯籠群。増上寺の各将軍霊廟に諸侯がこぞって奉納したものであろう。その数に少々圧倒される。
中を先に進むと灯籠群に四方を囲まれ、港区麻布より移築された井上馨邸の羅漢堂が佇む。その裏手の囲いの中にはおびただしい数の青銅製唐金灯籠群。増上寺の各将軍霊廟に諸侯がこぞって奉納したものであろう。その数に少々圧倒される。●石灯籠群

 参道を下り本堂に。もとは東本願寺から移築した堂宇があったとのことであるが、不審火にて焼け落ち、現在は鉄筋の建物となっている。その本堂を取り囲むように幾多の石灯籠が並ぶ。銘を見るに、増上寺とある。全国の諸侯より徳川将軍家、そしてその正室や側室に献上され、霊廟や参道に立ち並んだものである。
参道を下り本堂に。もとは東本願寺から移築した堂宇があったとのことであるが、不審火にて焼け落ち、現在は鉄筋の建物となっている。その本堂を取り囲むように幾多の石灯籠が並ぶ。銘を見るに、増上寺とある。全国の諸侯より徳川将軍家、そしてその正室や側室に献上され、霊廟や参道に立ち並んだものである。●第一多宝塔

 本堂右脇をすすむと第一多宝塔。大阪府高槻市畠山神社から移築したもの。その脇には桂昌院を供養する銅製の宝塔。桂昌院とは七代将軍家継の生母である。
本堂右脇をすすむと第一多宝塔。大阪府高槻市畠山神社から移築したもの。その脇には桂昌院を供養する銅製の宝塔。桂昌院とは七代将軍家継の生母である。●丁子門
 本堂の裏手にも無造作に石灯籠や常滑焼甕棺が並ぶ。将軍の正室や側室のもと、と言う。また、本堂裏の低地には丁子門。二代将軍秀忠の正室崇源院お江与の方の霊牌所にあったもの。本堂左手脇には滋賀県彦根市の清涼寺より移した弁天堂がある。
本堂の裏手にも無造作に石灯籠や常滑焼甕棺が並ぶ。将軍の正室や側室のもと、と言う。また、本堂裏の低地には丁子門。二代将軍秀忠の正室崇源院お江与の方の霊牌所にあったもの。本堂左手脇には滋賀県彦根市の清涼寺より移した弁天堂がある。本堂脇、左手の参道を上ると第二多宝塔。兵庫県東條町天神の椅鹿寺から移築。室町時代中期建立のものである。その右手には大黒堂。柿本人麿呂のゆかりの地、奈良県極楽寺に建立された人麿呂の歌塚堂を移築したもの。
●総門
 本堂下に総門が建つ。長州藩主毛利家の江戸屋敷にあったものを移した。この門は華美でなく、素朴でしかも力強い。いかにも武家屋敷といった、印象に残る門である。誠に、誠に、いい。この門に限らず、この不動院には徳川将軍家ゆかりの遺稿だけでなく、全国各地の由緒ある建物も文化財保存の目的でこの寺に移されている。
本堂下に総門が建つ。長州藩主毛利家の江戸屋敷にあったものを移した。この門は華美でなく、素朴でしかも力強い。いかにも武家屋敷といった、印象に残る門である。誠に、誠に、いい。この門に限らず、この不動院には徳川将軍家ゆかりの遺稿だけでなく、全国各地の由緒ある建物も文化財保存の目的でこの寺に移されている。●御成門
 正門に下る途中に御成門が迎える。これも台徳院霊廟にあったもの。飛天の彫刻があることから飛天門とも呼ばれる。都営三田線御成門駅の駅名の由来にもなっている門である。勅額門も御成門も共に重要文化財に指定されている。
正門に下る途中に御成門が迎える。これも台徳院霊廟にあったもの。飛天の彫刻があることから飛天門とも呼ばれる。都営三田線御成門駅の駅名の由来にもなっている門である。勅額門も御成門も共に重要文化財に指定されている。●勅額門
 石段を下りるとエントランスには勅額門。芝増上寺にあった台徳院こと、二代将軍秀忠の霊廟にあった門である。東京大空襲で残った数少ない徳川家ゆかりの建物のひとつ。勅額門とは天皇直筆の将軍諡号(法名)の額を掲げた門のことである。門の脇には御神木。この銀杏の大木は太田道灌が築いた江戸城址にあったもの、と言う。
石段を下りるとエントランスには勅額門。芝増上寺にあった台徳院こと、二代将軍秀忠の霊廟にあった門である。東京大空襲で残った数少ない徳川家ゆかりの建物のひとつ。勅額門とは天皇直筆の将軍諡号(法名)の額を掲げた門のことである。門の脇には御神木。この銀杏の大木は太田道灌が築いた江戸城址にあったもの、と言う。西武遊園地駅
 次の目的地は「隣のトトロ」の舞台モデル地のひとつと言われる「八国山緑地」。ひとりであれば、多摩湖(村山貯水池)をふたつに分ける村山上貯水池辺りから村山下貯水池の北を村山下貯水池堰堤まで歩くのだが、パーティの皆さんはそれほど歩きたい訳でもなさそうであり、狭山不動の近くにある西武球場駅から西武レオライナーに乗り西武遊園地まで進むことにする。西武園線西武園駅で下車。多摩湖堰堤にちょっと立ち寄る。
次の目的地は「隣のトトロ」の舞台モデル地のひとつと言われる「八国山緑地」。ひとりであれば、多摩湖(村山貯水池)をふたつに分ける村山上貯水池辺りから村山下貯水池の北を村山下貯水池堰堤まで歩くのだが、パーティの皆さんはそれほど歩きたい訳でもなさそうであり、狭山不動の近くにある西武球場駅から西武レオライナーに乗り西武遊園地まで進むことにする。西武園線西武園駅で下車。多摩湖堰堤にちょっと立ち寄る。八国山緑地

 多摩湖堰堤にちょっと立ち寄った後、いかにも西武園への入口といったエントランスの脇に沿って道を進み、八国山緑地の入口に。芝生の丘のむこうに森が見える。案内版によれば八国山の散歩道は何通りかあるが、今回は尾根道ルートを選ぶ。
多摩湖堰堤にちょっと立ち寄った後、いかにも西武園への入口といったエントランスの脇に沿って道を進み、八国山緑地の入口に。芝生の丘のむこうに森が見える。案内版によれば八国山の散歩道は何通りかあるが、今回は尾根道ルートを選ぶ。丘陵を登り尾根道を進む。いつだったか、以前この八国山を訪れたとき、雨上がりでむせかえるような木の香りに圧倒されたことを想い出した。森の香り・フィトンチッドではあった、
●トトロの森
この森のことを「トトロの森3号地」と呼ぶ。トトロの森は5号地まであり、八国山の対面、柳瀬川に開析された谷、といっても、現在は宅地で埋め尽くされてはいるのだが、その対岸の丘陵、狭山丘陵の東の端の鳩峰公園に隣接して「トトロの森2号地」。村山下貯水池の堰堤防の手前、清照寺方面に右折した堀口天満神社あたりから入る森が「トトロの森1号地」。狭山湖の北側に「トトロの森4号地と5号地」。1号地から5号地までは幾度かの狭山散歩の下りに辿った。 と、メモしながら確認のためにトトロの森をチェックすると、現在では29号地まで増えていた。直近で狭山丘陵を訪れた以降も、ナショナルトラストにより集まった基金で自然保護地区を増やしていったのであろう。
●ナショナルトラスト
はじめて「トトロの森」を歩いた時は、「隣のトトロ」の舞台となったモデル地故に「トトロの森」と称された、といった程度に考えていた。が、実際は狭山丘陵の自然を守る基金集めのキーワードとして、宮崎駿監督の承諾を得た上で「トトロの森」を冠したナショナルトラスト事業のことであった。
ナショナル・トラストとは、市民や企業から寄付を募り、自然や歴史的建造物などを買い取り保全され、後世に残そうとす運動のこと。明治28年(1895)に英国ではじまった。この狭山丘陵ではいくつもの市民団体により「トトロのふるさと基金」として誕生。平成3年(1991)に「トトロの森1号地」を取得、以後も活動を拡げ1998年に財団法人トトロのふるさと財団となって活動を続けている。その結果が29もの取得地となっているのだろう。
□宮崎駿監督
これも、いつだったか、清瀬を散歩しているとき、西武池袋線・秋津駅の近くに秋津神社があった、その神社の端から柳瀬川方向を見下ろすと豊かな林が目に入る。林に向かって小径を下ると湧水とおぼしき池、そして美しい雑木林が拡がっていた。林の中を彷徨うと「淵の森」とある。柳瀬川の両岸に拡がるこの森は、市民が自然環境を守るため活動を行っている、とのことである。 会長はジブリの宮崎駿さん。秋津三郎とのペンネームをもつ宮崎さんは、このあたりに住んでいる(いた)のだろう。柳瀬川を遡り、狭山丘陵の現在では「トトロの森」と名付けられた森のあたりを散策し、トトロの構想を練った、とも聞く。
将軍塚

 尾根道を進み将軍塚に。将軍塚のあたりが八国山の東の端。八国山の名前の由来によれば、「駿河・甲斐・伊豆・相模・常陸・上野・下野・信濃の八か国の山々が望められる」わけだが、木が生い茂り遠望とはほど遠い。
尾根道を進み将軍塚に。将軍塚のあたりが八国山の東の端。八国山の名前の由来によれば、「駿河・甲斐・伊豆・相模・常陸・上野・下野・信濃の八か国の山々が望められる」わけだが、木が生い茂り遠望とはほど遠い。将軍塚とは新田義貞が鎌倉幕府軍に相対して布陣し、源氏の白旗を建てたことが名前の由来。この地域で新田の軍勢と鎌倉幕府軍が闘った。府中の分倍河原で新田軍が鎌倉幕府軍を破った分倍河原の合戦に至る前哨戦であったのだろう。戦いの軌跡をまとめておく。
●新田義貞
元弘三年(1333)、新田義貞は鎌倉幕府を倒すべく上州で挙兵。5月10日、入間川北岸に到達。鎌倉幕府軍は新田軍を迎え撃つべく鎌倉街道を北進。5月 11日に両軍、小手指原(埼玉県所沢市)で会戦。勝敗はつかず、新田軍は入間川へ、鎌倉軍は久米川(埼玉県東村山市)へ後退。
翌5月12日新田軍は久米川の鎌倉幕府軍を攻める。鎌倉幕府軍、府中の分倍河原に後退。5月15日、新田軍、府中に攻め込むが、援軍で補強された幕府軍の反撃を受け堀兼(埼玉県狭山市)に後退。
新田軍は陣を立て直し翌日5月16日、再度分倍河原を攻撃。鎌倉軍総崩れ。新田軍、鎌倉まで攻め上り5月22日、北条高時を攻め滅ぼす。鎌倉時代が幕を閉じるまで、旗挙げから僅か14日間の出来事であった。
いつだったか東村山から小手指まで歩いたことがある。その折りに、久米川古戦場跡、小手指原の古戦場跡を辿ったのだが、小手指原の古戦場跡はそれなりの風情を伝えていたが、久米川古戦場跡は普通の公園といったものであった記憶が残る。
正福寺
 将軍塚から次の目的地である正福寺に向かう。八国山の尾根道から成り行きで丘陵を南に下り、新山手病院、東京白十字病院脇を抜ける。「隣のトトロ」の七国山病院のモデルとなった病院とか。
将軍塚から次の目的地である正福寺に向かう。八国山の尾根道から成り行きで丘陵を南に下り、新山手病院、東京白十字病院脇を抜ける。「隣のトトロ」の七国山病院のモデルとなった病院とか。○地蔵堂
道なりに進み都下唯一の国宝建造物の残る正福寺に。境内には鎌倉の円覚寺舎利院とともの禅宗様式の代表美を伝える堂宇が建つ。それが都下唯一の国宝建造物である地蔵堂である。上層屋根は入母屋造の?葺き(こけらぶき)で、下層屋根は板葺とのこと。元は茅葺(かやぶき)屋根だった、と。
いつだったかこのお寺様を訪れたときは、地蔵堂を囲む垣根は造り直されて間もないようで、お堂の渋さとシンクロしてはいなかったのだが、今回は風雪に耐え、堂宇と少しは調和するようになっていた。地蔵堂の前に案内。
●正福寺千体小地蔵尊像
「東村山市指定有形民俗文化財 正福寺千体小地蔵尊像
所在:東村山市野口町4-6-1 指定:昭和47年3月31日指定第11号
正福寺地蔵堂は千体地蔵堂と呼ばれるとおり、堂内には、多くの小地蔵尊が奉納されています。一木造り、丸彫りの立像で、高さが10-30cm位のものが大部分です。何か祈願する人は、この像を一体借りて家に持ち帰り、願いが成就すればもう一体添えて奉納したといわれます。
指定されている小地蔵尊は約900体です。背面に文字のあるものは、約270体で、年号のわかるものは24体です。正徳4年(1714)から享保14年(1729)のものが多く、奉納者は現在の東村山、所沢、国分寺、東大和、武蔵村山、立川、国立m小金井の各市にまで及んでいます。なお地蔵堂内には1970年代に奉納された未指定の小地蔵尊像約500体も安置されています。平成5年(1993)3月 東村山市教育委員会」
●正福寺千体地蔵堂本尊
 「東村山市指定有形文化財 正福寺千体地蔵堂本尊
「東村山市指定有形文化財 正福寺千体地蔵堂本尊所在:東村山市野口町4-6-1 指定:昭和48年3月31日 指定第12号 地蔵堂の本尊は、木像の地蔵菩薩立像で堂内内陣の須弥壇に安置されています。右手に錫杖、左手に宝珠をもつ延命地蔵菩薩で、像の高さ127cm、台座部分の高さ88cm、光背の高さ175cm、錫杖の長さ137cm。
寺に伝わる縁起には古代のものと伝えられ、また一説には、中世のものとも伝えられていますが、昭和48年の修理の際に発見された墨書銘によって、文化8年(1811)に江戸神田須田町万屋市兵衛の弟子善兵衛の作であることがわかりました。 平成5年(1993)3月 東村山市教育委員会」
□地蔵尊建立時期
「寺に伝わる縁起には古代のものと伝えられ、また一説には、中世のものとも伝えられていますが」とあるのは、本尊の延命地蔵菩薩は古代、長谷寺の観音像を像流した仏師であるとか、中世、北条時宗がこの地での鷹狩りの折り、疫病にかかり、夢枕に出た地蔵菩薩に救われたことを感謝して飛騨の匠をして七堂伽藍を造営したといった縁起があるが、その時に地蔵尊を造立した、と伝えられてきたのだろう。なおまた、地蔵堂の建立時期も昭和33年からの解体工事の際に見つかった資料により、室町時代の1407年の建立と推定されるようになった。
□千体地蔵信仰
千体地蔵信仰は、平安の中頃からひろまった末世思想の影響のもと、京都を中心に本尊に合わせて千体の小さな地蔵菩薩立像が並べられる幾多のお堂が現れる。功徳を「数」で現そうとして信仰形態。2000年に焼失した大原の寂光院、栂尾高山寺や蓮華王院三十三間堂にその形を残す。
しかしながら、この正福寺の千体地蔵は、上記信仰と少しニュアンスが異なる。案内にあるように、菩薩の功徳を数の多さで現した信仰とはことなり、願いを叶えた衆生の感謝の気持ちが集まった結果の千体、ということであろう。
□貞和の板碑
 貞和の板碑(じょうわのいたび)東村山市指定有形民俗文化財(昭和44年3月1日指定) この板碑は、都内最大の板碑と言われ、高さ285cm(地上部分247cm)、幅は中央部分で55cmもあります。
貞和の板碑(じょうわのいたび)東村山市指定有形民俗文化財(昭和44年3月1日指定) この板碑は、都内最大の板碑と言われ、高さ285cm(地上部分247cm)、幅は中央部分で55cmもあります。貞和5(1349)年のものです。碑面は、釈迦種子に月輪、蓮座を配し、光明真言を刻し、銘は「貞和五年己丑卯月八日、帰源逆修」とあり、西暦1349年のものです。
この板碑はかつて、前川の橋として使われ、経文橋、または念仏橋と呼ばれていました。江戸時代からこの橋を動かすと疫病が起きると伝えられ、昭和2年5月、橋の改修のため板碑を撤去したところ、赤痢が発生したのでこれを板碑のたたりとし、同年8月に橋畔で法要を営み、板碑をここ正福寺境内に移建したとのことです。昭和38年には、板碑の保存堂を設けたそうです。
東村山駅
所定の散歩ルートを終え、最寄りの駅である西武線・東村山駅に。この駅は西武国分寺線と西武新宿線が合わさる。駅の東口に大小ふたつの石碑が建つ。共に東村山停車場関連の石碑である。
●東村山停車場の碑
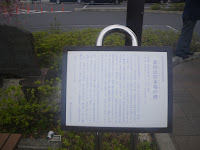 脇の案内に拠ると「東村山停車場の碑 東村山は北多摩地域でも早い時期に鉄道が開通した所です。明治二十二年(1889)に甲武鉄道(現中央線)の新宿と立川間が開通すると、やがてその国分寺と埼玉県の川越を結ぶ川越鉄道が計画されました。そして明治二十七年(1894)に国分寺と東村山間の工事が完成しましたが柳瀬川の鉄橋工事が難行したので、やむなく現在の東村山駅北方に仮設の駅(久米川仮停車場)を置き、国分寺‐久米川仮停車場間で営業を開始しました。翌明治二十八年(1895)鉄橋も完成し国分寺‐川越間が開通するのに伴い、仮設の駅は廃止されることとなりました。しかし、東村山の人々は鉄道の駅の有無は地域の発展に大きく影響すると考え。約二百五十人もの寄付と土地の提供により、同年八月六日にようやく東村山停車場の設置にこぎつけました。
脇の案内に拠ると「東村山停車場の碑 東村山は北多摩地域でも早い時期に鉄道が開通した所です。明治二十二年(1889)に甲武鉄道(現中央線)の新宿と立川間が開通すると、やがてその国分寺と埼玉県の川越を結ぶ川越鉄道が計画されました。そして明治二十七年(1894)に国分寺と東村山間の工事が完成しましたが柳瀬川の鉄橋工事が難行したので、やむなく現在の東村山駅北方に仮設の駅(久米川仮停車場)を置き、国分寺‐久米川仮停車場間で営業を開始しました。翌明治二十八年(1895)鉄橋も完成し国分寺‐川越間が開通するのに伴い、仮設の駅は廃止されることとなりました。しかし、東村山の人々は鉄道の駅の有無は地域の発展に大きく影響すると考え。約二百五十人もの寄付と土地の提供により、同年八月六日にようやく東村山停車場の設置にこぎつけました。時の人々の考えたとおり鉄道は地域の発展に欠かせないものとなり、その後の東村山の発展の基礎となりました。東村山停車場の碑は、こうした当時の人々の努力を後世に残すため、明治三十年(1897)に建てられたものです。 東村山市教育委員会」とある。
●鉄道開通100周年記念碑
 小さな石碑は「鉄道開通100周年記念碑」。石には「明治27年(1894年)国分寺 久米川間に川越鉄道が開通して今年(平成6年)で100周年を迎えました。 往時の東村山駅は現在より所沢寄りにあり、久米川停車場と呼ばれておりました。
小さな石碑は「鉄道開通100周年記念碑」。石には「明治27年(1894年)国分寺 久米川間に川越鉄道が開通して今年(平成6年)で100周年を迎えました。 往時の東村山駅は現在より所沢寄りにあり、久米川停車場と呼ばれておりました。私共は満100年の節目にあたり 歴史を振り返り、まちのさらなる発展と、これからのまちづくりを考える機会とするため、駅周辺の有志が集まり 写真展 お祭り広場 そして臨時列車「銀河鉄道」の運行など多くの記念事業を実施いたしました。
この事業を記念し未来の市民に継承するため碑をここに建立します。
平成6年9月吉日 鉄道開通100周年記念事業実行委員会」と刻まれていた。
□川越鉄道と東村山駅
川越鉄道は、明治22年(1889)に新宿と八王子間に開通した甲武鉄道の支線として国分寺から、当時の物流の拠点であった川越へと結ばれた。川越は江戸の頃から新河岸川(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)の舟運を利用し、川越近郊だけでなく、遠く信州・甲州からの荷を大江戸に送る物流幹線の拠点であった。
この舟運業で潤っていたためでもあろうか、「川越」を冠する川越鉄道ではあるが、その発起人には川越の商人の名は独りとしていない。舟運との競業を危惧したため、とも言われる。
同じく、立派な石碑の建つ東村山にも発起人はいないようだ。それでも駅ができたのは、上でメモした柳瀬川架橋の反対運動がきっかけ。柳瀬川架橋の長さが十分でなく、増水時に洪水を引き起こす原因になると激しい反対運動が起こり、橋梁の設計変更となったため工事が大幅に遅れることになった。そのため柳瀬川手前に暫定駅・久米川仮停車場を設け川越鉄を暫定開業した。
その後、橋梁が完成し、久米川仮停車場は廃止されることになるが、住民は停車場の設置を川越鉄道に陳情し、工事資金と用地を提供することにより、東村山停車場が開業することになった、とのことである。
●東村山軽便鉄道
 鉄道と言えば、東村山停車場の碑の右手に高層ビルがある。この地は村山貯水池建設のところでメモした東村山軽便鉄道の始点。大正9(1920)年に敷設された。
鉄道と言えば、東村山停車場の碑の右手に高層ビルがある。この地は村山貯水池建設のところでメモした東村山軽便鉄道の始点。大正9(1920)年に敷設された。
村山貯水池建設の砂利・資材は、中央線国分寺駅を経由し、川越鉄道で東村山駅まで運ばれ、駅前にあった材料置き場に集められた。軌道の違い故に、材料置き場で東山軽便鉄道に積み替えられた建設資材は南に少し下り、鷹の道(清戸街道)を右に折れ、村山貯水池の北を進み、現在の多摩自転車で右に折れ、武蔵大和駅へと北西に進む。ルートはそこでふたつに別れ、ひとつは村山下貯水池堰堤下に清美橋を渡って進む。もうひとつは宮鍋隧道を抜け貯水池内に入っていたようである。
本日の散歩はこれで終了。羽村・山口軽便鉄道の廃線歩きは、予想通り、あっけなく終了となったが、散歩の最後で、思いもかけず村山貯水池建設資材を運搬した東村山軽便鉄道始点辺りにも出合い、それなりに収まりのいいエンディングともなった。少し涼しくなったとき、今回パスした羽村から横田トンネルまでの羽村・山口軽便鉄道(羽村・村山軽便鉄道でもあり、羽村・村山送水路渠跡でもある)を歩いて見ようと思う。
同じく、立派な石碑の建つ東村山にも発起人はいないようだ。それでも駅ができたのは、上でメモした柳瀬川架橋の反対運動がきっかけ。柳瀬川架橋の長さが十分でなく、増水時に洪水を引き起こす原因になると激しい反対運動が起こり、橋梁の設計変更となったため工事が大幅に遅れることになった。そのため柳瀬川手前に暫定駅・久米川仮停車場を設け川越鉄を暫定開業した。
その後、橋梁が完成し、久米川仮停車場は廃止されることになるが、住民は停車場の設置を川越鉄道に陳情し、工事資金と用地を提供することにより、東村山停車場が開業することになった、とのことである。
●東村山軽便鉄道
 鉄道と言えば、東村山停車場の碑の右手に高層ビルがある。この地は村山貯水池建設のところでメモした東村山軽便鉄道の始点。大正9(1920)年に敷設された。
鉄道と言えば、東村山停車場の碑の右手に高層ビルがある。この地は村山貯水池建設のところでメモした東村山軽便鉄道の始点。大正9(1920)年に敷設された。村山貯水池建設の砂利・資材は、中央線国分寺駅を経由し、川越鉄道で東村山駅まで運ばれ、駅前にあった材料置き場に集められた。軌道の違い故に、材料置き場で東山軽便鉄道に積み替えられた建設資材は南に少し下り、鷹の道(清戸街道)を右に折れ、村山貯水池の北を進み、現在の多摩自転車で右に折れ、武蔵大和駅へと北西に進む。ルートはそこでふたつに別れ、ひとつは村山下貯水池堰堤下に清美橋を渡って進む。もうひとつは宮鍋隧道を抜け貯水池内に入っていたようである。
本日の散歩はこれで終了。羽村・山口軽便鉄道の廃線歩きは、予想通り、あっけなく終了となったが、散歩の最後で、思いもかけず村山貯水池建設資材を運搬した東村山軽便鉄道始点辺りにも出合い、それなりに収まりのいいエンディングともなった。少し涼しくなったとき、今回パスした羽村から横田トンネルまでの羽村・山口軽便鉄道(羽村・村山軽便鉄道でもあり、羽村・村山送水路渠跡でもある)を歩いて見ようと思う。

0 件のコメント:
コメントを投稿